2025年の大学受験結果が出てきました。
最難関の東京大学・京都大学への高校別の合格者数を見ると、定番の学校名が並んでいます。

筑波大付属駒場の東大合格者数は27人増の117人
大きな話題となったのは筑波大学附属駒場中学・高等学校が東京大学への高校別合格者数で2位に躍進したことかなと思います。昨年の4位から順位を上げ、合格者数も27人増の117人となりました。
筑波大学附属駒場中学・高等学校は中学入学が120人、高校入学が40人と1学年160人の生徒数ながら92名が現役で東京大学に合格(既卒生も含めると117人が東京大学に合格)、在校生に占める東京大学合格率は驚異的です。
1位の開成高校も149人と、依然として高い合格者数を維持していますが開成は1学年の生徒数が中学300名、高校400名と筑波大学附属駒場中学・高等学校の生徒数の2.5倍なので筑波大学附属駒場中学・高等学校の合格率が驚異的と言って良いでしょう。
また、公立高校の躍進も目立ちます。日比谷高校は81人、横浜翠嵐高校は74人と、それぞれ合格者数を増やし、上位にランクインしています。
埼玉県の県立浦和も含めて東京都、神奈川県、埼玉県の最難関公立高校から東京大学に合格者を輩出しているのは高校別合格者数で私立、国立の中高一貫校が上位を占める中で検討していると言えるのかなと思います。
また京都大学の高校別合格者数を見ると大阪府の北野高校、天王寺高校が1位と3位となっているほか、愛知の旭丘高校、滋賀の膳所高等学校、京都の堀川高校などTOP10に公立高校が5校入るなど公立高校が存在感を示しています。
高校授業料無償化で公立高校離れが懸念されていますが、質の高い教育を提供している学校が私立・公立問わず評価されていくのではないかなと思います。
医学部合格者数トップ3に桜蔭と豊島岡と都内の女子校2校
東京大学、京都大学以上に難易度が高い医学部受験ですが、医学部合格者数トップ3に桜蔭と豊島岡と都内の女子校2校が入りました。

女子高が減っている中で私立女子御三家の「桜蔭」「女子学院」「雙葉」から「雙葉」もTOP30にランクインしています。これは、女子の医学部志向の高まりや、女子校における医学部対策の充実が背景にあると考えられます。
一方で、東大や京大への合格者では各地の公立高校出身者が多かったのに対して医学部合格者数ランキングでは、公立高校からの合格者が少ないことが顕著です。この背景には、様々な要因が考えられます。
医学部進学における経済格差
医学部の学費は、私立大学を中心に高額になる傾向があります。そのため、経済的に余裕のある家庭の子供が医学部を目指しやすいという側面は否定できません。
また、医学部受験は、高度な学力だけでなく、面接や小論文などの対策も必要となります。これらの対策には、塾や家庭教師などの費用がかかる場合があり、経済格差が合否に影響する可能性も考えられます。
自治医科大学のような仕組みの必要性
自治医科大学のように、卒業後に一定期間、地域医療に従事することを条件に、学費を無償とする仕組みは、医学部進学における経済格差を是正する有効な手段なのではないかなと思います。
地域医療の担い手不足が深刻化する中で、経済的な理由で医学部進学を諦める人がいることは、社会的な損失です。自治医科大学の仕組みを参考に、より多くの人が医学部を目指せるような制度設計が求められます。
医学部進学における経済格差の問題は、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、今回のランキングをきっかけに、医学部教育のあり方や、地域医療の担い手育成について、より活発な議論がなされることを期待します。
医学部偏重の課題
近年、最難関大学受験において医学部の人気が非常に高く、優秀な学生が医学部に集中する傾向が顕著です。少子高齢化が急速に進む現状を踏まえれば、医療人材の育成が重要であることは言うまでもありません。しかし、日本のような資源の少ない国において最も優秀な学生層がこぞって医学部を目指す現状には、強い危機感を覚えます。
もちろん、医師という職業は社会的に非常に重要であり、高い志を持つ学生が医学部を目指すことは素晴らしいことです。しかし、AIをはじめとする最新のテクノロジー分野の発展が目覚ましい現代において、世界と伍してイノベーションを牽引できる人材の育成も、国家の発展にとって不可欠です。
医学部偏重の背景には、安定志向や高収入への期待など、様々な要因が考えられます。しかし、このような傾向が続けば、将来的に日本の産業競争力が低下する恐れがあります。
今後は、医学部だけでなく、理工系分野や人文社会科学分野など、多様な分野に優秀な人材が分散するような教育システムの構築が求められます。また、学生一人ひとりが、社会のニーズや自身の適性に応じて、進路を選択できるようなキャリア教育の充実も重要です。
医学部偏重の課題は、単に大学受験の問題にとどまりません。日本の未来を左右する重要な課題として、社会全体で真剣に議論し、解決策を見出していく必要があると考えます。
シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成
東大・医学部合格者ランキングの記事を読んで、安宅和人さんの『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』を思い出しました。
『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』は、AIとデータが社会を大きく変えつつある現代において、日本がどのように生き残るべきかを、膨大なデータと鋭い洞察力に基づいて論じています。
『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』の主な主張
- 日本の現状に対する危機感: 日本は、AIやデータの活用において、世界から大きく遅れを取っている。このままでは、国際競争力を失い、衰退の一途を辿る可能性がある。
- AI×データ時代の羅針盤: これからの日本は、AIとデータを最大限に活用し、新たな価値を生み出す「データ駆動型社会」を目指すべきである。
- 「異人」の重要性: これまでと同じ発想や行動様式では、変化の激しい時代を生き抜くことはできない。多様なバックグラウンドを持つ「異人」たちが、既存の枠組みにとらわれずに活躍できる社会を構築する必要がある。
『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』は、単なる現状分析や未来予測にとどまらず、私たち一人ひとりに、これからの日本をどのようにしたいのか、何をすべきなのかを問いかけてくる書籍だと思います。
- AIやデータが社会をどのように変えるのか?
- 私たちは、その変化にどのように対応すべきなのか?
- 日本は、どのような未来を目指すべきなのか?
これらの問いに対する答えは、一人ひとり異なるかもしれません。しかし、本書を読むことで、日本の未来について真剣に考え、行動するきっかけを得られるはずです。
TEDxTokyoでの安宅さんのプレゼン
東大・医学部合格者ランキングから考える日本の未来
今回の一連の記事で取り上げている「東大・医学部合格者ランキング」は、日本の教育や人材育成の現状を映し出す鏡と言えるでしょう。
『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』で指摘されているように、日本がAIやデータの活用で世界に後れを取っている現状は、教育や人材育成のあり方と深く関わっています。
ランキングから中学受験を頑張らせて最難関中高一貫校を目指させようと感じた方もいるのだと思いますが、『シン・ニホン AI×データ時代における日本の再生と人材育成』が示す未来への羅針盤を照らし合わせることで、日本の未来についてより深く考察できるはずです。
医学部偏重に対する関連記事の紹介
「東大医学部の4割が医者ではない道を選ぶ」という衝撃…過熱する医学部受験ブームで起きていること」として慶應義塾大学医学部特任助教、医師、博士(医学)の木下 翔太郎さんがPRESIDENT Onlineで記事を書かれています。
日本経済新聞でも「灘高生が東大理3離れ 医学部志向に異変の兆し?」として記事がアップされている。
この記事では
少子高齢化による人口減で、厚生労働省などでは40年までに医師過剰時代が来ると指摘する声が出ている。しかも人工知能(AI)の技術により、診断技術が革新的に向上したり、オンライン診療の普及で医療の効率化が進んだりすれば、医師のニーズが大幅に下がる可能性もある。医師になれば、高収入で社会的な地位もあり、一生安泰という神話が崩れるかもしれない。
日本経済新聞
とあり、東大を蹴って米マサチューセッツ工科大学(MIT)に進学した起業家の方の話なども紹介されている。
まとめ
東大・医学部合格者ランキングの記事を読んでいて、日本を牽引するべき子供たちの将来と合わせて日本の未来に関しても考えてしまいました。
中学受験の過熱が叫ばれる中で、保護者として子供たちの将来と合わせて日本の将来に関しても語り合ってもらう、きっかけになったら嬉しいです。
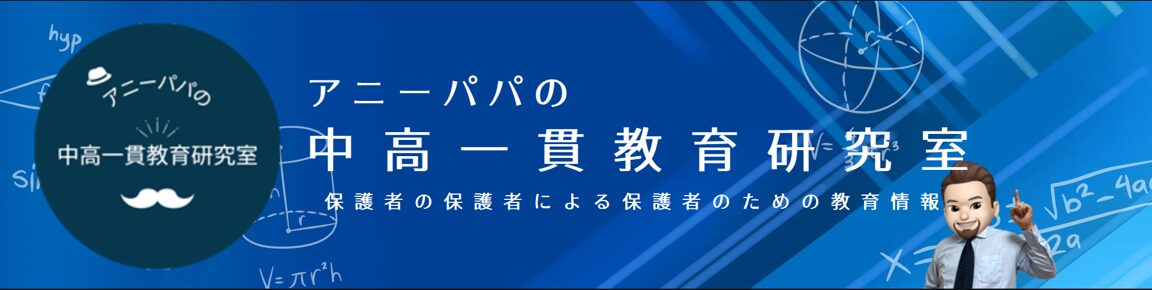


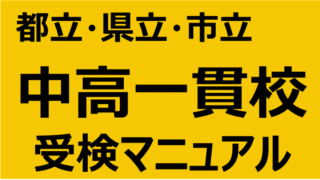




















コメント